こんにちは!香港で日本語教師をしているゆたか( @yutakanihongo )です。
私が香港で日本語教師をしているこの9年間で、学生が間違えやすい部分や母語に引っ張られやすい点がだんだんと見えてきました。
そのような点を知っていると、教師側はそれらを踏まえた練習を取り入れることができ、授業の幅がいくらか広がるかと思いますので、香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴をぜひご紹介したく思いました。
今回の記事は、香港で日本語を教えていらっしゃる日本語教師の方々に特にご興味いただける内容にはなりそうですが、当然香港以外にも広東語が母語の学習者は多いため、香港以外で日本語教師をなさっている方々のお役にも立てられたらと思っています。
また、広東語や外国語に興味がある方々など、言語学の観点からも面白いところがあるかもしれません。
それでは、下記リストの順にご紹介いたします。
■プロローグ
■香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴
1.発音
・ら行とな行の混同
・濁点/半濁点の有無
■まとめ:香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴を知ろう!

今回の記事はプロローグを含み、また、「1.発音」の中で例も多数挙げていることから、全体的にやたら長文になってしまうのを避けたく、ひとまずここでは「1」のみの紹介としました。
今後、②の記事も作成し、思いつく限り紹介を続けたく思っています。
なお、プロローグは広東語習得に関する私の過去についての話です。興味がない方は飛ばしてください。
プロローグ
私が香港へ来たばかりの頃、香港の主要言語である広東語については、「唔該(=ありがとう)」と「好食(=おいしい)」しか知りませんでした。
その後、同僚から聞くなどして1から10までの数字や、「呢個(=これ)」、「一個(=一つ)」などを覚えましたが、仕事がフルタイムで週六勤務なうえ、収入も低めだったため、体力的にも金銭的にも広東語を習いに行くのは不可能でした。
ただひたすら授業をこなす毎日でしたが、授業を通して学生が教えてくれた言葉や、学生の言動から自分で意味を推測して身に付けた言葉がありました。
後者の経験の中で、今でもその情景とともに鮮明に覚えているのが「藍色(=青)」「綠色」「黄色」「紅色(=赤)」「紫色」です。よほど印象的だったのか、9年も前のことなのにしっかり覚えています。
さて、私はどのように学んだと思いますか?
キッズクラスでは授業時間に余裕ができると、日本語の勉強もできるような遊びを取り入れていました。その一つがUNO、そして、もう一つが塗り絵です。
そう。これらの活動時に学んだのです。
UNOは、使い方としては単純にそのゲームをするだけだったのですが、ゲームをしながら数字や色を日本語で何と言うか教えていました。また、色替えのカードを使うとき、日本語で色を言うルールにしていました。
しかし、ゲームが白熱すると、子供達はつい広東語が出てしまうもので、色替えの時に広東語で言ってしまうことがありました。その時に彼らが発する言葉とその後の色を見て、「あ~、『紅色』は『赤』か~」などと理解していったわけです。
そして、塗り絵ではUNOには無い色も知ることができました。「紫色」です。
これは子供達が欲しい色鉛筆を探しているときに知りました。ある子が色鉛筆を探しながら「紫色(zi2 sik1)!紫色(zi2 sik1)!」と発していたのです。
『色』という単語はUNOでもう理解していたため、「何色のことを言っているんだろう?」と思っていたところ、その子が紫色の色鉛筆を手に取ったので、『紫色(むらさきいろ)』のことだとわかりました。
このようにして、ときどき身に付く広東語はありましたが、学校などで体系的に学ぶ機会はなく、ほとんど広東語がわからないまま時間だけが過ぎていきました。
そんな中、転機が訪れたのは香港へ来て5年が経った頃でした。
金銭面はいつも特別余裕があるわけではありませんでしたが、そうとは言え、以前に比べれば少しは学費を出せる状態になっていました。
また、運良く自宅から徒歩数分のところに語学学校があり、この距離なら仕事がフルタイム週六勤務でも、なんとか体力的に通えるだろうと思い、グループレッスンに申し込んだのです。
結論としては、その数ヶ月後に引っ越しすることになったうえ、職場での業務量や担当のコマ数も増えてしまったため、語学学校に通う時間が作れなくなってしまったのですが、短い期間でも初めて体系的に広東語を学習した経験はとても大きく、レッスンを受けていくうちに日本語と広東語の違いをたくさん知るようになりました。「だから学生はこれが難しいのか~!」と発見することが多々あり、非常に有意義な時間でした。

それでは、ここからが本編です!
本編では、自分が語学学校で学んで知った広東語の特徴も含めつつ、日本語の発音の中で香港人(広東語話者)が日本語学習で母語に引っ張られやすい点やつまづきやすい点などを紹介していきます。
香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴
1.発音
香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴の一つ目は発音です。
発音についてはどんな外国語を学ぶ上でも起こり得ることではありますが、日本語を学んでいる香港人(広東語話者)に見られる特徴として、いずれも広東語でその音の違いが曖昧なことから生じるため、いわゆる母語の干渉が原因と言えます。
・ら行とな行の混同
まずは、ひらがなの「ら行」と「な行」についてです。
これは、香港人(広東語話者)に日本語を教えたことがある教師の中では比較的有名な点ではないでしょうか。
広東語の発音では、日本語の「ら行」に近い「l」と「な行」に近い「n」の発音が曖昧になっています。
広東語の「n」は鼻音ではあるのですが、必ずしも鼻を使って発音しなければならないわけではなく、特に「n」が語頭にある場合は「l」の音と混同されてしまい、「l」で発音されることが多いからです。
実際、広東語で「あなた」を指す「你」の発音について、多くの場合、この発音(ピンイン)は「nei5」と書かれ、日本語話者としては「な行」だと思いますよね。
しかし、実際に広東語話者が喋っているのを聞くと、「ネイ(nei5)」と言っている人もいれば、「レイ(lei5)」と言っている人も…というか、むしろ「レイ(lei5)」と発音する人の方が多いように感じています。
このように、広東語話者にとっては「ネイ(nei5)」と言っても「レイ(lei5)」と言っても、「你」として伝わるようで、そのため、日本語の「ら行」と「な行」も区別しにくくなるというわけです。
この母語干渉が抜けない場合、例えば、下記のように、「からだ(体)」を「かなだ」と言ってしまったり、本人は「しらない(知らない)」と言ったつもりでも、実際の発音は「ら」が「な」になっていて、「しなない(死なない)」と発してしまっていたりすることがあります。
<例> 正:からだ(体) 誤:かなだ
正:しらない(知らない) 誤:しなない(死なない)
なお、鼻音と考えると、広東語の「ng」がありますが、これはこれで鼻を思いっきり使って発する音なので、日本語の「な行」とするには鼻音が強すぎてしまいます。
また、広東語の「l」と日本語の「ら行」、広東語の「~n(語尾の『n』)」と日本語の「~ん(語尾の『ん)』」等は一見似ているため、同じ音だと思う方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、細かく見ていくと、下記a.とb.のように発声時の舌の位置(動き)が異なっているのです。
a. 広東語の「l」:発声時、舌先で上の歯の裏をはじく
日本語の「ら行」:発声時、舌先を上の歯の裏から更に上部の歯茎に付ける
b. 広東語の「~n(語尾の『n』)」:発声時、舌先を上の歯の裏に付ける
日本語の「~ん(語尾の『ん)」:発声時、舌はどこにも付けない
こういった点も交えて「ら行」と「な行」を教えていくと、学生の混同がより防ぎやすくなるのではないかと思います。
・濁点/半濁点の有無
次は濁点/半濁点の間違いについてです。
これについても、母語干渉の影響があるのではないかと考えています。なぜなら、広東語の子音と日本語の子音は性質が異なるからです。
広東語の子音は「濁音/清音」という分類ではなく、「無気音/有気音」という分類になり、つまり、音が濁るのではなく、息を強く出すか出さないかの違いになります。
このような違いにより、日本語の清音/濁音/半濁音の区別が曖昧になるのではないかと思っています。
起こる事象をもう少し具体的に説明すると、清音の部分に濁点があるように感じたり、逆に濁点があるのに無いように感じたりする等です。
私の教授経験では、学生が「て形」を書く際に特に多いようには感じていますが、どんな単語においても発生する間違いと言えます。例として下記を紹介します。
<例> 正:飲んで 誤:飲んて
正:届いて 誤:届いで
正:せんげつ(先月) 誤:せんけつ
そして、実際に授業で起こった出来事として今でも覚えているのが、私が学生に何か質問をした際、文末に『か』と言ったのにもかかわらず、学生達から「『が』と言いました!」と突っ込まれたことです。
自分自身はもちろん親も祖父母も親戚も日本語ネイティブですし、日本で生まれ育っているので、疑問文の文末に『が』というのは絶対に言うわけがないのですが、グループレッスンで約半数の学生に突っ込まれ、とっても驚いたのを覚えています。
ひょっとして香港の人達は物凄く聴力が研ぎ澄まされているのでしょうか?
また、聴解でこの清音/濁音/半濁音の曖昧さが出てしまい、既習または既知の単語と結びつかなかった場合や、文脈から考えるとおかしい単語を思い浮かべてしまった場合、学生は当然わけがわからなくなり、ときどき突拍子もない発想もして、文の意味がさっぱりつかめない事態となります。
聴解文(音声)と学生の反応の例を下記a.とb.に紹介します。
<例> a. 音声:あの町は外国人(がいこくじん)が多いです。
聞き取った音:あの町はかいこくじんが多いです。
→学生「かいこくじん?それは何ですか?」
b. 音声:Aさんは外国の文化に興味があります。
聞き取った音【N1学習者】:Aさんは開国の文化に興味があります。
→学生「開国の文化?開国は国を開くことです。その文化がありますか?」
聞き取った音【N4学習者】:Aさんはかいこくの文化に興味があります。
→学生「かいこくの文化?かいこくは何ですか?」
そして、下記のように、濁音のところを半濁音にしてしまったり、逆に半濁音のところを濁音にしてしまったりすることがあります。
<例> 正:ボタン 誤:ポタン
正:アパート 誤:アバート
更に、学生の発話時に、「ら行とな行の混同」および「濁点/半濁点の有無」が同時に起こった場合、例として、下記のような発音を耳にすることがあります。
<例> 正:ぎゅうにゅう(牛乳) 誤:きゅうりゅう
まとめ:香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴を知ろう!
今回の記事では、香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴の第一弾として、発音についてご紹介しました。
日本語は他の言語に比べると、発音が正確でなくても相手に理解してもらえやすい言語だとは思いますが、それでも、相手によっては理解してもらえない時もやはりあり、理解してもらえないと少なからず学生の自信に影響するかと思います。
また、相手に理解してもらえたとしても、発音の良し悪しで相手が受ける印象は変わるもので、短い言葉やフレーズだったとしても、発音がネイティブみたいだったら、それだけで凄く上手だと思われて、感激してもらえることもあります。
教えている側としては、できる限り学生の成功体験が増えるような手助けをしたいですし、学生の発音がネイティブの発音に近くなればなるほど嬉しくなりますよね!
この記事が少しでも皆さまのお役に立てたら幸いに思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!


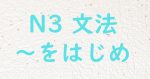
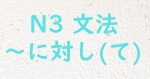






日本語を勉強している香港の人達って、どういうところで間違えやすいのでしょうか?特に苦手な部分などがあったら、知りたいのですが…。