こんにちは!香港で日本語教師をしているゆたか( @yutakanihongo )です。
前回、こちらの記事にて、日本語を学んでいる香港人(広東語話者)に見受けられる日本語の特徴として、まず発音について紹介しました。
今回の記事はその続きになります。香港で日本語を教えていらっしゃる日本語教師の方々はもちろん、香港以外で日本語教師をなさっている方々や、広東語や外国語に興味がある方々のお役にも立てられたら幸いです。
それでは、下記リストの順にご紹介いたします。
■香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴
2.漢字に頼る
3.アクセント(音の高さ)
■まとめ:香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴を知ろう!
香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴
2.漢字に頼る
香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴の二つ目は『漢字に頼る』です。これは、本や読み物等、主に読むことで日本語を学習するタイプの学生に見られやすい特徴です。
広東語で使われる漢字と日本語の漢字には同じものが多数あるので、日本語の文章の中で漢字だけを見て、その文章のおおよその意味が理解できる香港人(広東語話者)の学生は多いと思います。
漢字を見て意味が理解できるというのは日本語を学習するうえで非常に有利な点ですが、時に弊害となることがあります。
その文章の中に知らない言葉がある場合、文章全体の意味を理解するためには、そのわからない一部は意味を推測して文章全体を理解しようとするでしょう。このようなケースは構わないと思います。
しかし、文章の中で漢字を追って理解することが癖になってしまうと、「漢字を見ることで意味を理解する」というのが習慣になってしまうのです。
その漢字を見るだけで意味がわかってしまったら、読み方を覚えるのは後回しにしてしまうという気持ちはわからなくもないです。

実際、私の広東語学習でも、後から読み方(ピンイン)を調べるときがあります。
例えば、動画を見ているとき、話を止めずに、ひとまず最後まで見たい場合等。時々、そういうことがあるのは仕方がないと思いますし、後で読み方を調べてメモをしたり、読む練習をしたりすれば問題ないと思います。
しかし、しっかり読み方を調べず、また、漢字を見ることで意味を理解していくのがしょっちゅうになってしまうと、後になってますます問題が大きくなってしまいます。
この問題に直面している学生を以前教えたことがあります。
漢字を見て(文章を読んで)理解するのが習慣になると…
その学生はN1の合格を目指していました。語彙も文法もよく知っているし、話すことも、少し広東語訛りはありましたが、ある程度できていました。
しかし、大きな問題がありました。この学生はいつも日本語で書かれた本やパンフレット等から日本語を勉強してきました。そして、その本やパンフレットの漢字には振り仮名がありませんでした。
そのため、漢字を見て意味は理解できるものの、正しい読み方は身に付いておらず、私との会話や聴解でその言葉が使われても、認識できなかったのです。つまり、学生が知っている漢字の言葉が会話や聴解で聞こえても、学生の頭の中でマッチしない状態でした。
N1を目指している段階でこの状態は大変なことで、学生自身も困っていましたし、私も頭を抱えました。
N1の聴解練習をしていると、その中に出てくるN4、N3レベルの言葉でも認識できないことがあったので、N1の勉強よりも、N4、N3レベルの単語を使った初歩的な聞き取り練習を採り入れました。それは、会話や文章ではなく、ひらがなで数文字程度の単語だけを聞いて、3つの選択肢から正しい読み方を選ぶというような練習です。
日本語能力試験はマークシート方式ですし、一般的にマークシート方式の試験は、知識や能力が多少あやふやでも合格できてしまうことがありますよね。合格は本当に素晴らしいことですが、N1レベルに来て、実際の聴解能力がN4、N3となると、N1合格の壁は本当に分厚いです。
この学生の他にも、N1合格を目指していて、聴解だけ間違いの連続という学生がいました。知っている単語なのに聞き取れず、その単語を漢字で書いてみたら、「あ~!〇〇!」となっていました。この学生も日本の小説を読むのが好きでした。
上記二名は「漢字に頼る」という特徴が顕著な例ですが、大なり小なり似たような特徴を持っていた学生は結構いました。
レベルが上がった先で必要以上に苦しむことがないように、学習者の皆さまには読むことばかりで日本語を学習するのではなく、早い段階で音声からも学習する(字幕なしや音声だけ聞く)ことをオススメしたいですし、教える側も漢字に頼れないような授業や活動を頻繁に採り入れるのが良いかと思います。
3.アクセント(音の高さ)
香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴の二つ目は『アクセント(音の高さ)』です。
既習単語のアクセントに引っ張られる?
日本語は、広東語に比べると音の高さの分類はかなり少ない言語ですが、それでも影響するときはあります。有名なのは「雨」と「飴」や「橋」と「箸」などです。
ここではその2つの例について話しますが、そのアクセントは学生が初めに習う方に引っ張られる傾向があると感じています。
例えば、「雨」と「飴」の場合、大抵は「雨」の方が早い段階で習います。
それが原因か、「飴(あ↗め)」と言いたい時に、「雨(あ↘め)」のアクセントで言ってしまう学生が多いことに気が付きました。
「橋」と「箸」も同様に、「箸」の方が習うのが早いことが多いので、「橋(は↗し)」と言う時に、「箸(は↘し)」と言ってしまったり、存在しないアクセント(「は→し→」等)で言ってしまったりする場面に遭遇しました。
アクセントを間違えても通じるので、曖昧になる?
日本語は広東語と違って声調がなく、言葉の中でどこを高く発音するか低く発音するかだけに焦点があります。高いか低いか二つに一つなので、話す時にその高低を間違えたとしても、聞いている相手は他の単語や文脈から正しい言葉が容易に推測できることがほとんどです。
例えば、「喉が痛いので、あ↘めを買いました」と言っても、「飴(あ↗め)」のことだとわかってもらえるでしょう。喉が痛いと言っているし、何より、雨を買うことはできませんからね。
また、町を探索中に日本人に「あっちに行きたいんですが、は↘しはどこですか?」と言った場合も、外にいて向かい側に行きたいというときに必要なのは当然「橋」ですし、どこかへ行きたいと言っているときに箸が必要な場面はなかなか無いと思います。
更に、日本人と一緒に食事するとかレストランにいる等の食事の場で、もし「は↗しはありますか?」と言ったとしても、きっと「箸(は↘し)」のことだとわかってもらえるでしょう。食事の時に橋が必要な状況は、基本的にありませんからね。
このように文脈や状況から簡単に正しい言葉が推測できることがわかるかと思います。
そして、相手の言いたいことがわかれば、わざわざ訂正しない日本人も多いと思うのです。教師なら訂正するでしょうけど、一般の日本人で「それは、は↗しじゃなくて、は↘しですよ」等とわざわざ訂正する人がどのくらいいるでしょうか。

ちなみに、私が今まで英語圏の人達と英語で話してきた中で、英語を訂正されたのはたった1回でした。
私は大学生の時に初めてネイティブの人と話す機会がありました。つまり、それぐらい英語を話す機会がない生活でした。そんな私なので、いくら頑張って勉強していても、間違いは相当あったはずです。それなのに、訂正されたのはこれまでの人生で1回だけなのです。
この自分の経験からも、言いたいことが伝われば、文法やアクセントに間違いがあったとしても、ネイティブはわざわざ訂正しないと考えています。
そういうわけで、日本語を勉強している香港人(広東語話者)の方々も、「アクセントが違うから日本人にわかってもらえない」という経験はそれほど多くはないだろうと推察します。
また、母語が広東語という面からも、日本語を話すときのアクセントが曖昧になりがちではないかと感じています。なぜかと言うと、広東語の方がアクセント(音の高さ=声調)が圧倒的に多いからです。
多い(複雑な)ところから少ない(簡単な)ところへ行くと、気持ちに余裕ができて、それほど細部まで気にしないことがあるのではないでしょうか。
例えば、料理でも、目玉焼きを作る時とオムライスを作る時では集中力が違うと思うのです。料理ができない人が目玉焼きを作るときは100%の度合いで集中するでしょう。
でも、オムライスを作ることができる人が目玉焼きを作るときはどうでしょうか?目玉焼きなんて余裕だと思って、60%ぐらいの集中力で作ると思いませんか?
私はなんだかそのように感じるため、香港人(広東語話者)の方々が日本語を学ぶときも、アクセントを細かく気にしない人もいるのではないかと思うのです。
同音異義語の区別が難しくなる
アクセントを間違えて話しても相手にわかってもらえて、訂正もされなかったら、そのままそのアクセントが身に付いてしまい、中級・上級へ進んでいってしまいます。
当然、日本語のレベルが上がっていくにつれて、同音異義語が増えていきますが、N5だけでも既に複数の同音異義語が存在します。
例えば、「きた」。これは漢字を使うと、「来た」、「着た」、「北」の3つがあります。この中で「来た」だけアクセントが違い、「来た(き↘た)」です。そして、他の2つはアクセントが同じで、「着た(き↗た)」と「北(き↗た)」です。
この「きた」については、「着た(き↗た)」と「北(き↗た)」が同じですが、意味が全然違ううえに、一方は動詞、もう一方は名詞で品詞も違うので、区別しやすいかもしれません。
でも、品詞が同じ言葉もあります。例えば「えき」です。
N5では「駅」だけですが、N2で「液」が出てきます。これも意味は全く違いますが、どちらもアクセントが同じ「え↘き」なので、しっかり覚えていないと、「えき」と聞いて「液」に結びつかないという事態になります。
更に複雑なものの例としては、「こうえん」があります。
N5では「公園」だけですが、N3以降になると「公演」、「講演」、「好演」、「後援」が出てきます。これら全て「公園」と同じアクセントです。
このような場合、それぞれの漢字の違いを覚えるのはもちろんですが、意味もしっかり頭に入っていないと、聴解で出てきた際に、どの「こうえん」を意味しているのかわからなくなります。
「公園」しか認識できない場合と、「公園」と「公演」、「講演」の3つだけ認識できる場合、また、上記5つ全てを認識できる場合とでは、聴解の理解度・正答率が大きく異なります。
香港人(広東語話者)の方々にとっては日本語のアクセントはとても簡単だと思いますが、このように学習が進むにつれて、ますます弊害が出てくるので、語彙を教える際には正しい音の高さも身に付くように、教師側も意識して教えることが望ましいと感じます。
まとめ:香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴を知ろう!
今回の記事では、香港人(広東語話者)の日本語学習者に見受けられる日本語の特徴の第二弾として、漢字に頼ることとアクセント(音の高さ)についてご紹介しました。
どちらの問題も、やはり学習レベルが上がるにつれて、解決するための壁が厚くなりますので、教える側としては理想はゼロ初級から、途中から教えることになった際にはその時からでもしっかり注意していきたい点です。
この記事が少しでも皆さまのお役に立てたら幸いに思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!



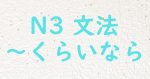
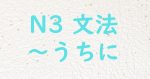





日本語を勉強している香港の人達が間違えやすい部分について知りたいです。発音の他に何か苦手な部分などあるのでしょうか?